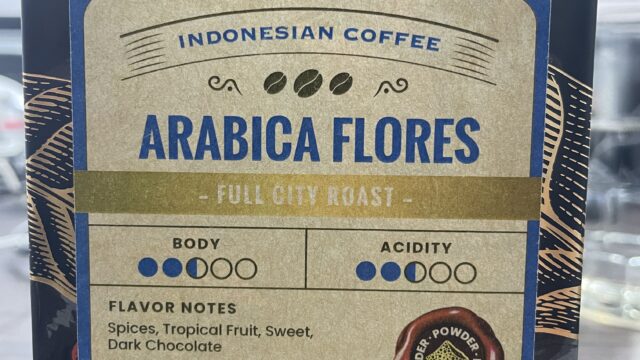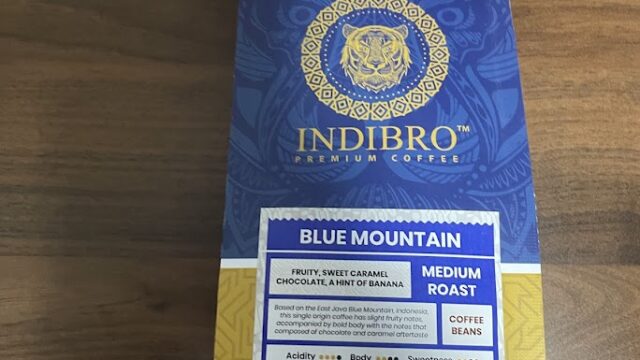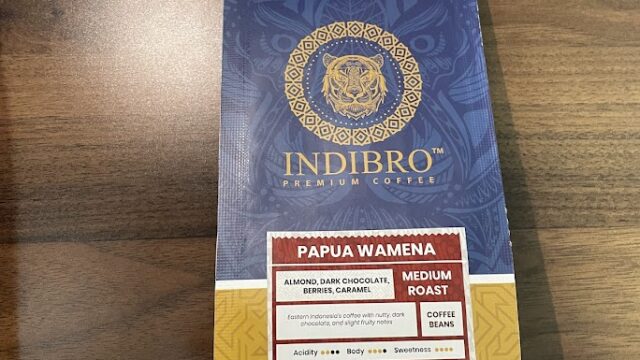インドネシアのスラウェシ島(Sulawesi)は、海に囲まれた立地と内陸の高地が共存するため、魚・肉・米の食材が豊かに集まります。街角の食堂や市場を歩けば、湯気と香辛料の匂いに包まれ、旅のハイライトが「食」になること間違いなし。とりわけ魅力的なのは、ご飯を主食に、汁物や魚・肉をおかずにするという、どこか日本の食卓と通じるスタイルが根づいている点です。以下では、肉 → 米 → 魚の順にスラウェシの食文化を紹介します。

① 肉料理の王様:牛テールと牛テールスープ(Sop Buntut)
スラウェシの食堂で頻繁に目にするのが、牛テールを使った牛テールスープ(Sop Buntut)。牛の尻尾を骨ごとコトコトと煮込み、スパイスで仕上げる一杯は、骨の髄の旨みとほどよい脂が溶け出し、スープ全体にコクが広がります。長時間煮込まれたテール肉はホロホロに崩れ、レンゲでほぐして頬張るたびに満足感が押し寄せます。
旅行体験:マカッサルの食堂で食べた一杯は、約1,000円ほど。椅子に座ると同時に漂ってくる湯気とスパイスの香り、器を持ち上げた瞬間に感じる“濃さ”。口に含むと、思わず「ぎゅうぎゅうしいほど旨みが詰まっている」と感じるほどでした。脂っ気はありつつも重すぎず、むしろスルスル飲めてしまう不思議なバランス。

日本との比較:この「肉の旨みをスープに溶かし込む」発想は、こってり系ラーメンやすき焼きの割り下が染みた煮汁にも通じます。現地の人が白ご飯やBurasをスープに浸して食べる様子は、ラーメン+ライスの満足感そのもの。はじめてでも抵抗なく楽しめるのは、この味覚の地続きがあるからでしょう。

② 米文化の主役:Buras(ブラス)と“米のやつ”
スラウェシを歩くと、食生活の中心に米があることを実感します。代表的なのがBuras(ブラス)。ココナッツミルクで炊いた米をバナナの葉で包み、蒸したり煮込んだりする素朴な主食で、包みを開くとほのかな甘みと独特の香り、モチモチの食感が現れます。日本で言えば、ちまきやおにぎりに近い存在で、持ち運びがしやすく、日常から行事まで幅広く登場します。


おすすめの食べ方:牛テールスープにBurasを落として食べると、たちまち雑炊のような一体感が生まれます。素朴なBurasがスープの旨みを吸って化ける瞬間は、まさに日本の味噌汁+ご飯やお茶漬けの延長線。香り・温度・食感が同時に立ち上がり、体の芯から満たされる感じがします。
米の多様性:白ご飯に加えて、ナシ・ウドゥッ(ココナッツ風味のライス)やナシ・クニン(ターメリックの黄色いご飯)など、香りや色で楽しむバリエーションも豊富。これは日本の炊き込みご飯や赤飯の文化を連想させます。米を中心に据え、おかずで世界を広げる設計思想は、日本と驚くほど近いのです。
③ 海の恵み:Bawal(バワール)とBandeng(バンデング)
海に囲まれたスラウェシでは、魚料理も生活に根づいています。Bawalは日本のスズメダイやヒラアジに近い印象で、香ばしく焼く/カラッと揚げるが定番。味付けは塩+ライムの潔いシンプルさで、ご飯が際限なく進みます。Bandeng(ミルクフィッシュ)は骨が多い一方、身は柔らかく旨みが濃い魚。スープにも揚げ物にも向き、日常の食卓を支える存在です。
旅行体験:港町の屋台で食べた揚げBawalは、衣がカリッと音を立てて割れ、中からほろりと身がほぐれました。そこへライムを絞り、湯気の立つご飯を一口。思わず「焼き魚定食にライムを足したような清々しさだ」と感じたほど。隣のテーブルでは家族連れがBandengの骨を器用に外しながら、スープとご飯を交互に頬張っていて、日本の食卓の風景と重なって見えました。
日本との比較:塩と柑橘で味を締める感覚は、塩焼き+すだち/カボスに近く、魚+ご飯+汁物という日常の組み合わせが、そのまま旅先でも機能します。スパイスの強い料理が続いても、魚が挟まると舌がリセットされるのも、日本の献立思想とよく似ています。


まとめ:確かにスラウェシ料理は日本人好み?
スラウェシの食文化は、牛テールと牛テールスープ、Burasを中心とする米料理、BawalやBandengの魚料理がご飯中心の食卓で共存する姿に凝縮されています。香辛料や調理法はインドネシアらしく個性的なのに、根本の設計は日本の「ご飯+おかず+汁物」と地続き。だからこそ、初めてでも親しみやすく、同時に新鮮です。
旅行者には、牛テールスープにBurasを落とし、焼き魚をおかずに白ご飯を頬張る一食をぜひおすすめします。湯気、香り、温度、食感が一度に立ち上がるその瞬間、「日本っぽいのに全然違う」という感覚が、旅の記憶に深く刻まれるはずです。